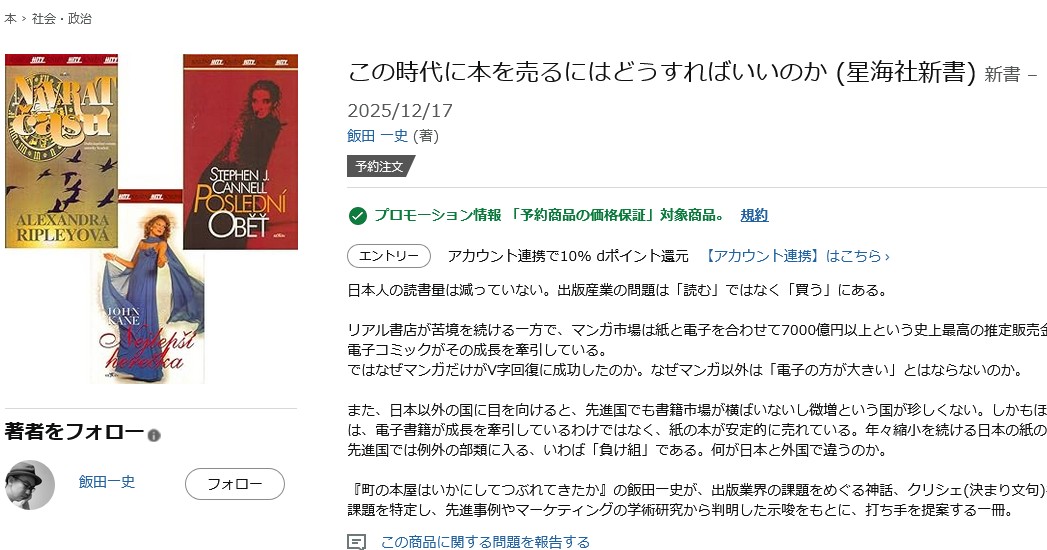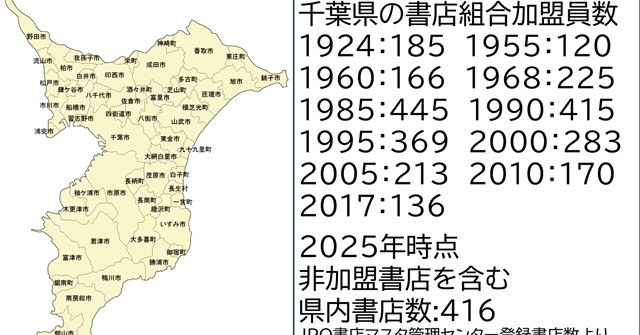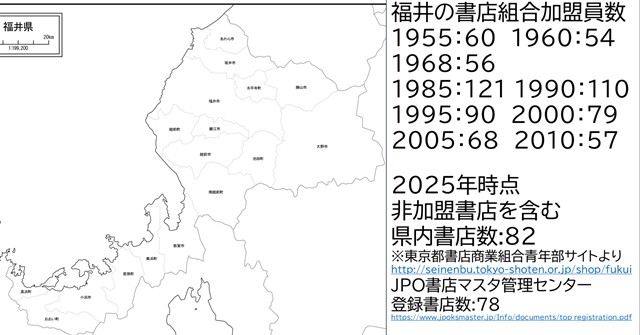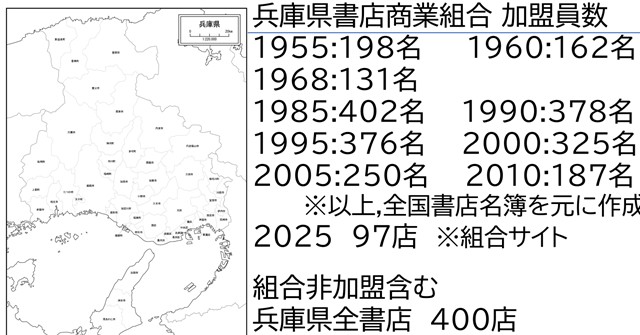vol.14 2021年上半期ベスト本
一冊ずつ詳しく書こうと思っていたのですが息子が朝5時に起きてきていっしょに遊ばないといけなくなったので、簡単に……。記事を書いたものについてはそちらをお読みいただければポイントがわかるかと思います。
島村一平『ヒップホップ・モンゴリア』
松本佐保『アメリカを動かす宗教ナショナリズム』
月刊サイゾー2021年4・5月号にも関連記事を書いています。ドラッカーが(反共勢力としての)アメリカのキリスト教諸団体にコンサルに入っていて、いまの福音派メガチャーチ中興の祖であるボブ・ビュフォードに請われてコミットしていた(ドラッカー自身は福音派ではない)話など。
木村絵里子編著『場所から問う若者文化』
石田光規『友人の社会史』
かねもと『私の息子が異世界転生したっぽい』
よしながふみ『大奥』
朝井リョウ『正欲』
アバンティーズ『1/4の風景』
萩尾望都『一度きりの大泉の話』
喰らってしまって読後1週間は引きずりました。
それ以上は、この本について何を言っていいのかわかりません。
澁谷智子『ヤングケアラー わたしの語り』
こうして並べると重たいこと、なかなか人に言えないことを描いたものが自分のなかでとくに記憶に残っているようです。そういうのが好みなんでしょうね。あまり意識してこなかったですけど。
ただただ楽しいものの価値が世の中で軽んじられがちなので、そういうものの価値を謳っていきたい気持ちが強いですが、自分の「地」の部分は別に明るくもないし積極的な人間でもないので素直に選ぶとこうなりました。
■今週気になったニュース
storywiz ウェブ小説「しっ!あいつをお願い」ドラマで制作(韓国語)
一般的に、Web小説がドラマや映画などで製作されるまでは「ウェブ小説連載→出版契約→映像化」の過程を経る。ストーリーウィズはこれとは異なり、無料連載作のOSMU(One Source Multi Use)の可能性を早期に発掘し、源泉IPとしての価値を最大化するために、映像化と出版契約を同時に迅速に推進した。
DAUMウェブトゥーンがKAKAOウェブトゥーンに改編
もともと会社としてDAUMとカカオが合併して今のカカオがあるわけですが、ひとつの時代の終わりを感じます。あとこういう合併して集約してコングロマリット化していく韓国のやりかた、アメリカっぽいですよね。日本は会社ごとくっついて強者連合になっていく感じではない。
小学館など7社、7月に「ZUKAN MUSEUM GINZA」オープンへ
KADOKAWAが図鑑に参入
当たればでかいですが制作の手間・コストも膨大なのが図鑑。
学校1人1台コンピューター「一見よさそう」の落とし穴
学びの質を研究してきた東大名誉教授の佐藤学さんに聞いてみた。「実は、ICT(情報通信技術)教育が学力向上につながるというエビデンスはほとんどないのです」最も信頼できるのが、国際学習到達度調査(PISA)の調査委員会が2015年にまとめた報告書だという。先進国の集まりであるOECD加盟の29カ国のデータを分析すると、学校でコンピューターの使用が長時間になると、読解力も数学の成績も下がっていたという。衝撃的な内容だ。
このまとめ方は悪意があるというか恣意的なリードの仕方です。
そもそもPISAの言う「読解力」(リーディングリテラシー)はデジタルデバイスを使って情報処理するリテラシーを含んでいて、2010年代以降、その度合いはどんどん高まっている。
で、日本の子どもは圧倒的にアナログで教育されていて他のOECD諸国と比べて出遅れているから日本もGIGAスクール構想やらないとやばい、というのが出発点にある。
それなのに、ICTを使った教育はダメだ、デジタル教科書はダメだ、タブレットは害悪だという議論に持っていったらそれこそOECDの言う「読解力」は身につかないんですけど。
もちろん文科省のやりかたや現状の教育ソフトウェアに問題なしとは思いませんが、そもそもPISAで言われる読解力が今どんなものを指し示しているか(時代によって力点が変化しているので)の説明なしに「デジタル教育は読解力を下げる」ともっていくのは問題ありかと。
■outro
2021年の上半期に出た本といえば自分が関わった単行本も2冊あるのでよろしくお願いします。
後半に出る単行本は今のところ予定がないですが、単行本仕事は増やしていきたいと思っています。
すでに登録済みの方は こちら