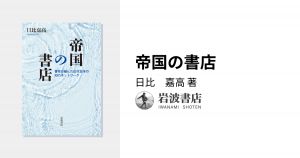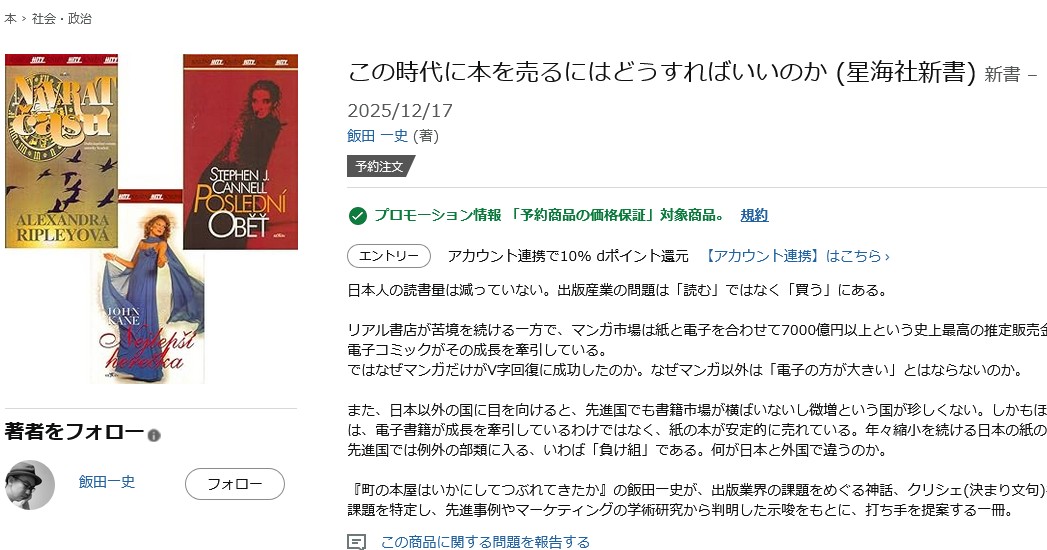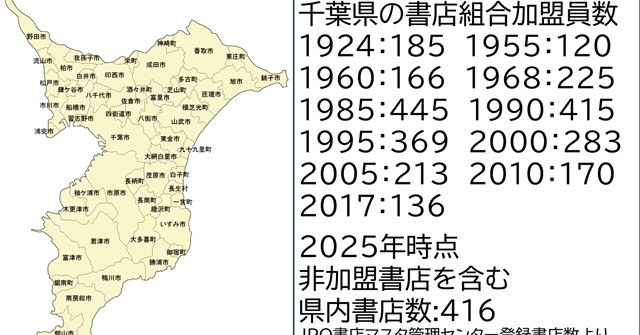日本と韓国の出版流通システムはいかに分岐したのか
2025年2月、長野県の学校図書館問題研究会に講演で呼んでもらった際に、松本駅周辺の観光をした。
駅からしばらくまっすぐ歩いた先にある旧制高等学校記念館に行くと、バンカラな戦前の男子学生のすごした日々を示す展示があり、3階にのぼるとそんな学生の銅像があった。

筆者撮影
3階の展示をぐるりと見終えて銅像の裏側に回るとおどろいた。プレートには「京城帝国大学 京城帝国大学予科 同窓会」とあったからだ。当時、京城(いまのソウル)にあったものなのか、あとで作ったものなのかわからないが、いずれにしても外地(植民地)にも旧制高校があったと気づかされて、複雑な気持ちになった。

筆者撮影
日帝は「内鮮一体」を謳っていたから、朝鮮人で日本語を学び、京城の旧制高校に通った若者も4割弱いたらしい。しかしその点に関する特別の言及は同記念館内にはなく、わずかに地図上で外地も含めてどこに旧制高校があったかを示すのみである。
旧制高校では英語、ドイツ語、フランス語が必修だった。
ということは京城の学生たちも現地で外国語の辞書や洋書を入手していたはずだ。もちろん、日本語で書かれた教科書もだ。
それらの本をどこから買ったのか? 京城にあった書店で調達していたはずである。
先日、三省堂書店でトークイベントをしたさいに三省堂の社史を調べたのだが、三省堂は戦時中に京城、台北、新京(満州)、昭南(シンガポール)に支店を置いている。 先ごろ刊行された日比嘉高『帝国の書店』(岩波書店)によると、三省堂のほかに今日も残る大手書店では、たとえば丸善も外地に出店している。
なぜ三省堂や丸善だったのか。推察するに、大手であればどこでもよかったわけではなく、教科書や辞書、洋書の流通にノウハウのある事業者でなければ務まらなかったからではないか。
戦前の書店業において、教科書販売が収益基盤としてきわめて重要だったことはしばしば指摘されている(教科書販売が多い、つまり納入している学校が多い書店ほどランクが高い扱いを受けたと三省堂の社史にも書いている)。
『帝国の書店』では外地書店においても教科書販売が重要だったことを記している。
私は韓国漫画・ウェブトゥーン史についても書いているので韓国の出版産業や書店流通についても調べているのだが、韓国の出版産業は光復以降、および韓国戦争(朝鮮戦争)以降も教科書や学習参考書をはじめとする教育書を中心に発展し、今でも中核に位置している。
たとえば韓国出版文化産業振興院『出版産業実態調査』を見ると出版事業体別の売上額のシェアは学習誌(学業に必要または役に立つ補助教材。定期的に出版され、家庭などに配達される本)が全体の3割、教科書および学習参考書が2割、その他受験書や学術/専門書も含めると、教育関連書で紙の本の全体の約6割を占めている。
日本の出版関係者が韓国に出張・旅行したときによく行く大型書店の教保文庫や弘大(ホンデ)などにある独立系書店、あるいはマンガ・アニメ・ラノベに強い総販しか見ないと実感しづらいのだが、韓国の街中にある普通の書店に行くと、店の面積で最大規模を占めているのは学参やドリル、教育書、学習マンガ(企画漫画)である。
韓国漫画博物館があり、毎年漫画・ウェブトゥーンフェスティバルを開いている冨川(プチョン)市の本屋でさえそうだ。
これは「韓国は受験戦争が激しいから」という理由だけでは説明がつかない。
李斗暎『韓国出版発展史 1945~2010』(出版メディアパル)によれば、韓国では出版社と書店間での定価販売の協約は1977年まで成立せずに割引合戦が横行して書店・卸・版元は疲弊し、倒産が相次いだ。
77年の合意もあくまで業界内協約にすぎなかったために1990年代にディスカウントショップが台頭すると割引販売が横行し、実質的に定価販売はまたも崩壊する。
2003年に図書定価制の法制化がなされるが、IT産業優遇の国策もあってオンライン書店のほうが値引きできる状態になって町の本屋の減少に歯止めをかけることはできなかった。
その後、2014年に図書定価制は改正されてオンライン書店優遇がなくなるまで、かなりの時間を要したのである(なお「図書定価制」と呼称されているが最大10%、ポイント等も合わせると実質15%まで割引できるし、新刊発売後12か月経ったものは定価を変えられる)。
こうした背景を考えると、教科書が乱売合戦を逃れた数少ない出版物であったことが無視できない。
『韓国出版発展史』と『帝国の書店』を合わせて読むと、興味ぶかい点がいくつもある。
『帝国の書店』では外地書店は内地と同じ「定価販売」を組合規定で強いられていたが、外地は輸送コストがよけいにかかっているのだから割増販売させてほしい、と現地の組合は嘆願している。つまり朝鮮半島内も戦前は定価販売だった。しかし今述べてきたように、戦後は定価販売は崩れている。日本のように独禁法の適用除外というまわりくどいやりかたを取ってメーカー(出版社)による小売店(書店)への価格拘束を法的に許容するのか(これがいわゆる著作物再販制と呼ばれている、再販売価格維持契約)、ドイツやフランスのように「本は定価販売」とダイレクトに法制化するのか、どちらのやりかたもあっただろう。だが、軍事政権下の韓国はそうしていない――「アメリカ式の自由市場経済だ」と内外に示したかったから、という可能性はあるが。
『韓国出版発展史』では、定価販売の協約がない状態で1950年代に委託販売が導入されたことで出版社はとにかく部数を刷って撒く「雑誌の黄金時代」が一瞬登場したが、フタをあければ書店からの資金回収に苦労し(なにしろ書店も割引合戦にはげんでいたから、手元に十分な現金がない)、バタバタと倒れていったことを記述している。
同書では委託販売が新しい手法であったかのように書かれているが、出版物の委託自体は日本では明治から徐々に広がっていったものだ。買切への回帰は1940年代に日配が強制したことで生じたのであり、戦後に委託は復活している。外地では内地への返品コストを考えると委託は実質不可能で買切だった可能性が高いと思うが、この点は『帝国の書店』を読んでも判然としない。
また、これは筆者が韓国で翻訳エージェントや翻訳家を務めている宣政佑氏(韓国漫画・ウェブトゥーン史の共著者)から聞いた話だが、韓国の出版業界で「委託」と言ったときには本来の委託販売(版元から預かって書店が販売し、売れるか委託期間が終わったあとで精算する)であって、日本の出版業界のような返品条件付販売、すなわち、取次から本屋に本が届いたらその分の代金は翌月末までに払わなければならない「実質先払い」ではないという。
戦後韓国でも、委託と言いつつ返品条件付販売で書店に実質先払いさせていれば「出版社が書店から資金回収できなかった」ということは少なかったはずだ。
日本で本来の委託から返品条件付販売にいつのまにか変わったのは間違いないが、その移行時期は調べてもよくわからなかったことを拙著『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』でも書いている。ただ韓国と日本では「委託」で指し示すものが違う点が、時期の推定のヒントになるかもしれない。
また、宣政佑氏によると、日本では大手取次に対して書店が口座を開こうとする(取引しようとする)と求められる「信認金」(保証金)もないという。では植民地時代にあったのかなかったのか、ここも不明である。
1940年代に入ると日本では日配が結成され、当時数百あったとされる取次をすべて召し上げてひとつの会社で一元的に出版流通させる統制的な手法に移行する。
『帝国の書店』によれば満州では同様のしくみの独自組織「満配」を立ち上げることに成功した一方で、「鮮配」は失敗して「日配朝鮮支部」にゆだねられた。
戦後日本では日配が完成させた、取次がどの書店に何冊配本するのかを実質的に決めるという統制的な配給システムが大手取次に継承され、神田村の中小取次を合わせても日本出版取次協会の構成員は100に満たず、トー日販の圧倒的なシェアを前提とした出版流通となる。
ところが韓国は軍事政権のもとで「検閲」は延々と続いたにもかかわらず、日配のように国が出版流通を一元化する機構を設けることはなかった。ジャンルや地域別に多種多様な「総販」(取次)が乱立し、書店間の仲間卸も珍しくないという、日本でも日配以前に見られた姿に着地する。
大日本帝国が内地と外地で共通の出版流通システムを構築しようとし、一定程度は達成されたにもかかわらず、当然ながら日本と韓国ではその後のあゆみは分かれている。
しかし実際のところどちらがどのていど「戦前」(日帝時代の思考や制度)を引きずっているのかはなんとも言えないところがある。
たとえば日本における「配給」的な発想に基づく取次の見計らい配本のしくみや、組合側から働きかけて再販契約を実現させ、定価販売や発売日協定を守らない事業者には実力行使も辞さなかった書店組合の動きは「統制的」と呼ぶしかない。
一方で韓国で教科書販売が産業の基盤となった点、検閲などを通じての出版物の内容への介入は、日帝からの連続性で捉えざるをえない点である。
また、日本では書店マージン改善を求める「適正利潤獲得運動」は牛歩の歩みで今も「適正利潤」とされた書店の粗利25%をベースとする条件は成立していない。
ところが1950年代初頭、内線下の韓国では書店マージン25%、卸5%の条件に不服を申し立てて「委託の場合は40%だ!」と書店団体が雑誌不買も含めた大きな運動を2度展開している。失敗に終わったようだが、韓国では日本の書店が求める粗利25%が「ベース」になっている点に注目したい。日配時代には確実に25%も書店の取り分がなかったはずだ。日本が日配から戦後取次に移行する時点で大きく条件を変えられなかった点も、韓国とは大きく異なる。早々に25%まで引き上げられていたら、いまの本屋の景色も、ずいぶん違ったことだろう。
……と、こんな話を9月7日(日)の東京 西荻窪・今野書店さんでの日比嘉高先生との対談で深掘っていきたいと思っているので、ぜひご来場およびオンラインチケットでのご参加よろしくお願いします。
■告知
アーカイブ配信チケットが9/8まで買えますのでぜひ!!! ↑
こちらもオンラインチケットあります
ちょっとだけ私の発言も紹介されています
『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』(平凡社新書)がノミネートされました。単著がアワードにノミネートされたのは初なので非常にうれしいです。全国の丸善、ジュンク堂各店でフェアがありますのでぜひ足を運んでみてください。
疲労が蓄積してしばらく体調不良、気力の低下が著しかったのですが少し回復してきました。でも金曜夜まで外で仕事があると土曜にNewsletter発行する気力が起きないとわかったので今日書くことにしました(いつもは土曜日発行)。むりのない範囲で発信していきます。
すでに登録済みの方は こちら