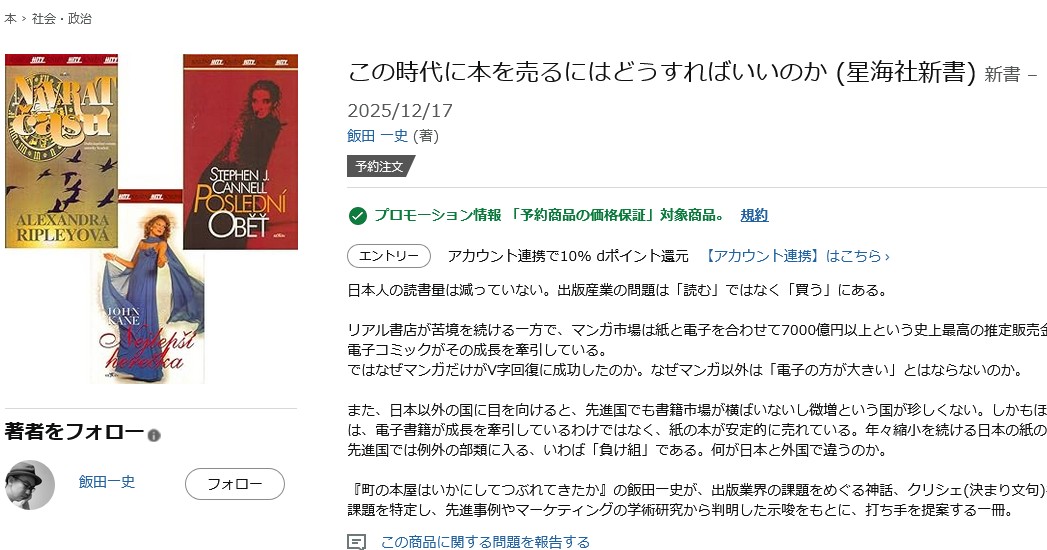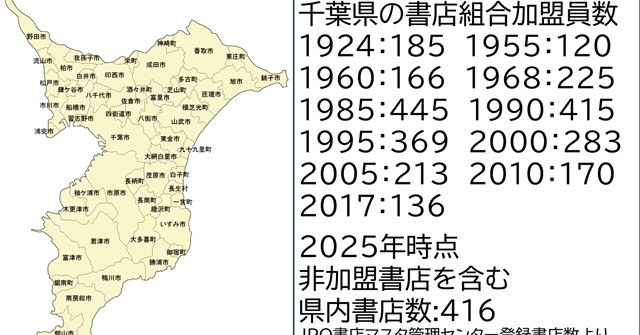中高生は「読みやすく、主張がわかりやすい」文章を書くために必要なものが「語彙」だと誤解している
『作文ぎらいのための文章教室』という本を書くにあたって、知り合いの学校の先生から中高生の書く文章の特徴についてヒアリングし、また、中高生にアンケートを採らせてもらった。
ここでわかったのは、10代が「良い文章」だと考えているものと、そういう文章を書くために必要だと考えているものとのギャップである。
はっきり言ってしまうと「そこを第一にがんばっても、君たちが良い文章だと思っているものに近づくには遠回りだよ」と思った。どういうことなのか少し解説したい。
まず「あなたにとって”良い文章”とはどんな文章ですか?」と尋ねてみた。
1位:読みやすい、主張や伝えたいことがわかりやすい
2位:簡潔
3位:構成が明確
※自由回答でアンケートを採り、筆者側でグルーピングして整理した
「読みやすい」「わかりやすい」がトップだった。「簡潔」「構成が明確」については、大人が聞いても違和感はないだろう。文章作成とは直接は関係ないが、このアンケート結果は読書推進をしている人たちにも認識してもらいたいところだ。
ところが「良い文章を書くためには、何が必要だと思いますか?」ときいてみると、「おや?」という結果になった。
1位:語彙力
2位:経験、練習
3位:構成力
もうダントツで「語彙(力)」という回答が多かった。なお「読書」と答えた生徒は少数派だった。
さて、「読みやすく、主張や伝えたいことがわかりやすい」「簡潔」「構成が明確」な文章を書くために、もっとも必要なことは「語彙力」だろうか?
普通に考えると、これではゴール設定とそこに至るための手段がミスマッチである。
もし「語彙がたくさんあれば読みやすい文章が書ける」なら、辞書を引きまくって書けばいいという話になるが、そんなわけはない。言いまわしだけが豊富でも、それはわかりやすさとは関係がない。
「文章をつくる」作業を2つに分けると
「中身」と「伝え方」になる。言い換えると「何を」×「どう書くか」だ。
本の感想にしても小論文にしても、まずはネタだし、素材集めをして「何を作るのか」を決めるところから始まる(先に「切り口」を設定する場合もあるが、細かい話はさておく)。
それを適切なフォーマット、つまり「伝え方」に落とし込んでいく。
語彙は基本的には後者の「伝え方」、それも一部分に関わるだけだ。
本来、文章を書くときの重要度で圧倒的トップに来るようなものではない。
「文章を書くときに、どういうことがイヤですか? 文章を書くときに、どんなことに悩んでいますか?」と聞くと
1位 うまくまとめられない
2位 字数制限。規定の文字数に収めること
3位 書くことが思いつかない、言葉が出てこない
だった。
「うまくまとめられない」「字数制限」は「伝え方」の課題。
「書くことが思いつかない、言葉が出てこない」は「中身」をどう引き出し、作るかという課題だ。
そしてこの三大お悩みは、語彙をいくら増やしても、それだけではほとんど解決できない。
中高生が考えているように「訓練、練習」はもちろん必要だが、やみくもに書きまくっていれば自然と身につくという話でもない。
「学校で文章の書き方について教わったことで、パッと思いつく内容はありますか?」に対してはほぼ同じくらいの割合で
・小論文のテクニック(「序論→本論→結論の順に書く」「主張→理由→具体例→反駁→主張の順に書く」など)
・国語のテストで求められるテクニック(「文章の要約や現代文の記述では具体例は書かない」「記述問題は制限字数の8割以上書く」「文のはじめ、終わりに書いてあることを抜き出す」など)
・作文のテクニック(「原稿用紙は最初の1マス空ける」「話し言葉を用いない」「ら抜き言葉にしない」「主語、述語をはっきりさせる」など)
に上位は集約された。
つまり学校では、作文、小論文、国語科の試験において求められる「様式」、つまり「伝え方」のフォーマットは教えている。
しかし、生徒が求めている「書くことが思いつかない」「うまくまとめられない」「語彙力向上」にダイレクトに応えるカリキュラムはどうも不十分のようだ(学校にもよると思うが)。
したがって
・ネタ出しをして「書くこと」を作る方法
・ネタ出しをしたあと「主張」を作る方法
・主張に合わせて、ネタだしした材料を取捨選択して並べ直し、文章の流れを構成する方法
このあたりに大きな需要がある。
これは教育関係者、司書、学参や児童書の編集者に知ってもらいたいポイントだ。
一方で、教員からのヒアリングからは「生徒は作文でも小論文でも弁論大会の原稿でも、全部『こういうフォーマットを使うとまとまるよ』と教えると、コピーして身につける」しかし「文字数が変わったり、違うタイプの文章を書かせたりすると途端に破綻する」といったものがあった。
ようするに、数学の公式を覚えるようにして文章の書き方もパターンで覚えるので応用がきかない。
そもそもなぜそのパターンが求められているのかを考えずに様式だけ採り入れている。
これはひとことで言えば「読者が不在」なのである。
読む相手が求めているものを整理してから書けば、お手本になるフォーマットがなくても要点をおさえ、伝わる文章になる。しかし、相手のことを考えていないので、お手本がないと何を書けばいいかまったくわからなくなってしまう。
「文章の書き方」は知りたいが、送られた文章を読む側のことは頭から抜けている。
あるいは「学校で求められてる文章ってこんなもんでしょ」という勝手に設定した枠のなかに収まるように書いてくるので、つまらない。
したがって中高大生に文章の書き方を伝えるさいには、特定のフォーマット、パターンありきではなくて、まず、
・読む相手はどういうひとで
・何を求めているのか
・その文章を読んだ相手がどうなったら成功なのか
・文章を読んだ相手がどうなってくれたら、自分は満足なのか
こういうことから考えよう、と伝えたほうがいい。
……というもろもろを物語仕立てで書いているのが『作文ぎらいのための文章教室』です。ぜひ大人から手渡していただければありがたいです。
■告知
先日の紀伊國屋書店新宿本店での吉成信夫さんと田口幹人さんとの「書店と図書館の連携」についてのイベントを記事化しました。
ベネッセまなびライブラリーについて取材。「本の感想を書いてほしいが、なかなかアウトプットは消極的」「端末やサイト上に検索機能はあるが、特定のキーワードしか使われない」という図書館あるあるに対する導線の作り方、および、他社も含めた学習参考書・問題集の電子図書館サービスへの拡張についてきいています。電子図書館をチャレンジタッチ利用者の30%が月1回以上使っているというのはなかなかすごいことだなと思いました。
若者の読書について講演します。8月17日夜に参加者のキックオフミーティング的なものがあるようですがそちらも参加します。
8月26日(火)夜に横浜駅すぐ近くのネイキッドロフトにて横浜の本屋の戦後史と今を語るイベントを妙蓮寺の石堂書店、本屋生活綴方の中岡祐介さんとやります。私のほうでは有隣堂おもしろ話などを準備しています。
先日出演した『視点・論点』、NHKプラスで観られます。ではまた来週。
すでに登録済みの方は こちら