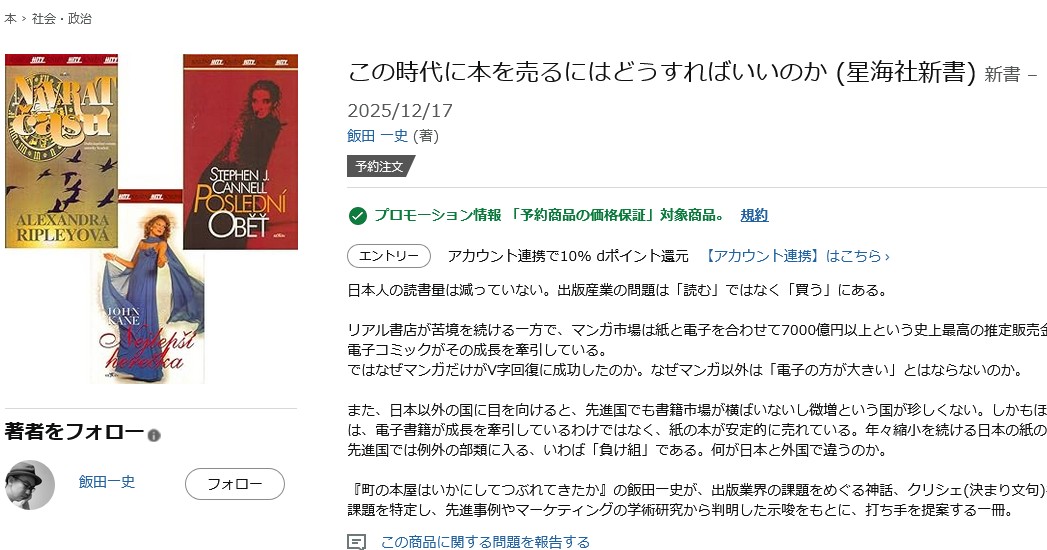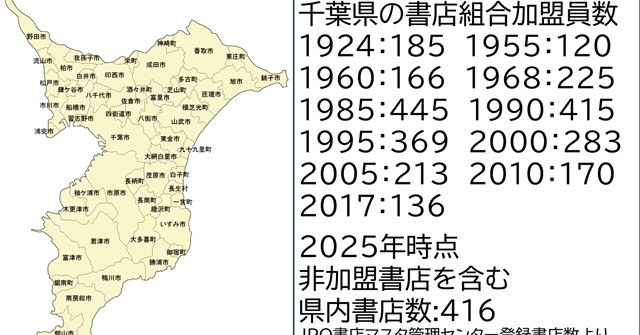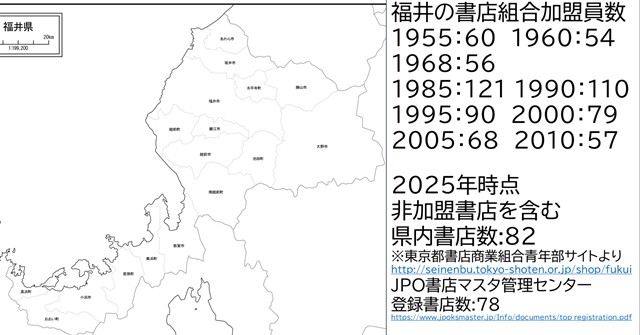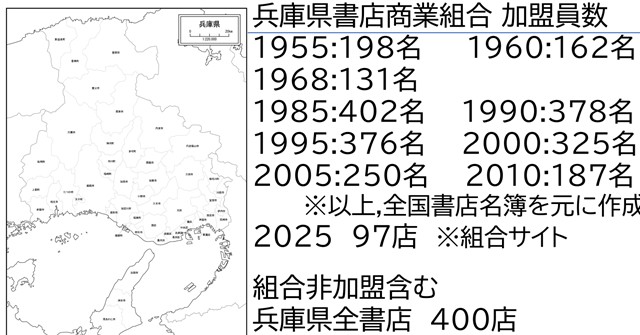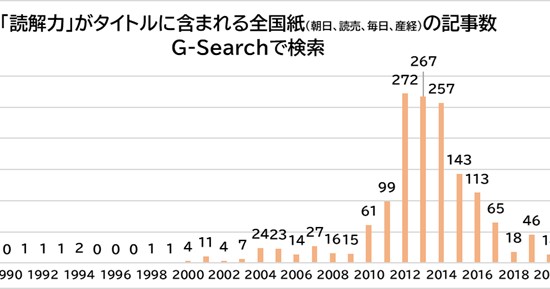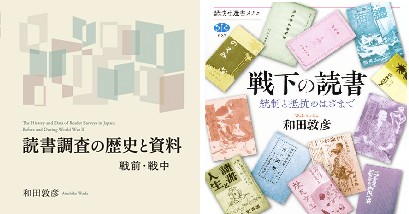「文学フリマやZINEについてどう思いますか?」
■告知
『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』合わせで大垣書店のPodcast「新刊さんいらっしゃい」に出ました。6/27に配信されました。大垣書店となるべく絡めてお話させていただきました。
三省堂書店神保町本店で7月4日(金)よるにイベントやります。三省堂の知られざる歴史をひもときながら、今後の書店像を考えます。三省堂、やってきたことも実はおもしろいし、公式の社史でエグいところ、会社の暗部や失敗まで掘り下げているというなかなか珍しい会社です。楽しいトークにしたいと思っています。アーカイブ配信もありますので時間の合わない方、遠方の人もぜひ。
7月22日(火)に大阪、阿倍野の新しい本屋 亜笠不文律さんでトークイベントします。次の日、図書館向けの講演がありますので泊まりでいきます。終わったあともお話する時間が取れると思いますので大阪の方、ぜひ。大阪の書店の歴史も少し調べていきます(大阪は公刊されている組合の刊行物が充実しているので。あ、亜笠さんは組合入ってないと思いますが)。
ひっそり子どもの本についても書いています。センシティブな話なので、表現に問題があったら直します(連絡ください)。
先日の版元ドットコム会員集会での『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』の版元向けの講演動画です。
■今週のコラム
『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』刊行後のイベントや取材で「文学フリマやZINEについてはどう思いますか」とよく質問される。
「本屋はしんどいのに、イベントやリトルプレスは盛り上がっている」という対比で訊いているのだと思うが、まず思うのは「誰目線の話?」である。
ZINEや文学フリマを私が個人的にどう思うかという話なら「自分で本作ったり売ったりするのって楽しいよね!」以上。である。
しかし聞きたいのはおそらく「本屋の事業、ビジネスとしてどういう意味を持ちうるのか」だろう。
文学フリマはイベント。ZINEは出版物。だから、分けて考えるほうがいい。
断っておくと私は会場が幕張メッセになってからの文フリには行っていない。だから最近の事情は知らない。ただブックフェスはいくつか見ている。そのくらいの人間が書いたものとして読んでほしい(的外れなこともあると思う)。
また、文フリには本屋からの出展は比較的少ないと思うし(作り手のイベントだから)、小規模書店にはそんなところに出ていく余裕はない、売る商品もない、といった意見もあると思う。だが全国数千軒の本屋の事情をすべて汲んで語ることはできない。あくまでここでは「出た場合」の仮定の話であり、したがって「出られる書店」しか前提にしていない(出ない書店にとっては「関係のない話」としか言いようがない)。
本を売るイベント(文フリに限らず、地域のブックフェスティバルなども含む)に関して、私が見聞きしている範囲で、多くの人から
「イベントだと本が売れるし、楽しい」
「でも、出展の手間や交通費、運送コストを考えると厳しい」
という声がある。
前者だけしか言わない人・事業者にとっては「よかったね」で終わり。
しかし後者の声が意外に多い。
そう考えると、本の即売会イベントは、本屋が事業として考えて出展する場合には、単純にZINEや本を売るだけでは、商売としては微妙ということになる。
本の定価・マージンを考えると、店売りだけでなくイベント出展でも兼業・複合店化した方がいい。
売上=客数×客単価×頻度
だが、頻度を上げることはその場では不可能である。
したがって取りうる選択肢としてパッと思いつくのは
1.客単価を上げるか、粗利の高い商材とくみあわせる
2.今後の継続的な潜在顧客を獲得する機会と捉えてリスト(メアド)を獲得する
のいずれかだろう。
1はZINEや本屋に絡めたTシャツなどのグッズを売るとか、著者や本屋とチェキをいっしょに撮れるとか(誰が嬉しいのかは知らないが)。あるいはオンラインイベントのチケット、読書会チケット、選書サービスを売るなどでもいい。
2はどういう意味か。
そのブースに来ている顧客のメールアドレスを獲得し、Newsletterを登録してもらう、といったかたちで中長期的に本やサービス、その書店自体の案内が届く関係性を作ることができれば、その場で十分な収益化ができなくても、LTV(生涯顧客価値)で見れば出展コストがペイする、という発想だ。
もちろんそのためには直接なんらかのかたちでリスト(メアド)を得る必要があるし*、出展者が定期的に発信していることが前提になる。
*たとえばチラシにお試し的な内容を印刷しておいてQRを読んで登録を促す、「その場でQRを読み込んでNewsletter登録してくれたら○円引き」的なアレなど。
さらに、そのイベントが「地元のイベントへの出展」なのか「地元外への出展」では、その場で販売すべきものや案内すべきものもやや変わってくるだろう。
地元や比較的近隣のイベントに出た場合、そのイベントの趣旨を汲んでその場に来るであろう客層に寄せつつ、自分の店にリアルに来てくれることを前提にアピールする場にするのが普通だと思う。
その上で、ニッチでローカルでおもしろいZINEやイベント企画(たとえば地域史や地元の有名人、著名スポット、フードなどと絡めたもの)を案内すれば、地元民には刺さりやすいのではないかと思う。
もちろん、本屋自身がZINEや書籍を作っていなくても地場のリトルプレス、出版社、あるいは地元で活動している個人や地域の出身者と協業してもいい。
こういうイベントは「出展者は出ずっぱりで他のブースを見る機会がない」ことになりがちだが、本当であれば今後のために営業、コネクションづくりにつなげられたらいい。
シェア本棚の棚主募集をイベントでしてもいいかもしれない。
地元外のイベントへの出展の場合、その後、リアルに店に来店してもらう(とくに継続的に来てもらう)ことは期待できない。
したがってその場の品ぞろえ、取扱商品で「特色あるな」と思ってもらって、その後、その本屋のECショップやオンラインイベントに、地域外の人も買いたいと思えるものを用意しておく(誘導する)必要があるだろう。
イベントでどこでも売っているようなものを売っていたら、なおさらそのあと来てもらうのはむずかしい。
くりかえすが、本屋が商品・サービスをすべて自分で用意する人はない。手が回らないとかノウハウがないならすでにやっている誰かと組めばよい。「組みませんか」とオファーされた側にとって販路拡大、売上アップなどの明確なメリットがあり、お互いの相性がよさそうであれば、普通に検討してくれるはずである(文脈や価値観を共有できなそうな場合はむずかしい)。
■ZINE
ZINEは本屋にとっては「仕入れて売る」と「作る」の2つの立場がある。
「仕入れて売る」に関しては、仕入れや精算の手間はあるし、店の規模にもよるが、自店の客層に合ったものを選んで仕入れることができれば(目利きができれば)悪い商売ではないと思う。
これはある独立系書店の方が言っていた(やっている)ことだが、ZINEは再販契約の対象外である。
価格決定権を書店側が持つことができる。
掛け率も、委託か買い切りなのかも交渉次第である。
したがって、ためしに委託で仕入れて売れ行きを見つつ、もっと売れそうなら「買い切りにするから掛けを下げて」と言って追加で発注をかけたり、あるいは客足を見ながら値段を上げ下げできる。
出版社から出ている本なら書店店頭で2万円分売っても粗利4400円くらいのところ、ZINEならたとえば卸値1000円で仕入れて売価2000円で10冊売ったら粗利1万円になる。
ZINEを作る、それも趣味ではなく本屋のビジネスとしてやる場合はどうか。
事業として捉えるのであれば、広告と絡めるのが売上を安定させるためには必要だと思う。
たとえ100部、200部であってもテーマやエリアに合っていれば(確実にそこにいる人たちに届けば)広告主にとっては意味がある。
客単価が高いビジネス、ひとりのお客が半年なら一年なり契約するのが当たり前なビジネスなどであれば「10万出してもいいよ」みたいな場合はある(「2万円なら」というのを何社か集めるでもZINEの制作費はまかなえるだろう)。今はどこも人手不足だから、採用目的の広告出稿もありうる。
「地域を盛り上げるために出す」といった大義名分があればお金を出してくれる個人・企業もいるかもしれない。出す価値を証明できるような過去の実績は必要だろうが、地元企業のことをいい感じで紹介するZINEや本を作れば広告だけで真水で数十万、あるいは100万単位でお金にすることもできるだろう。そこまで来るともはや本屋というより版元だが、製造小売業兼広告業というのは日本の出版業の歴史では過去にも存在した業態であり、回帰したにすぎない。
あるいは「ZINEを出したあとにイベントをやります」「読書会・ランチ会・飲み会をやります」ということまで組み込んで、先回りして特定の飲食店と話を付けておけば、その店からの広告も期待できるし、イベント収益も見込める。
相互に送客できるとわかれば飲食店のなかにZINEを置いてもらうこともできるだろうし、本屋への導線もできるだろう。
これも立地や価格設定等にもよるが、関わった人が誰も損しない、疲弊しないかたちでコミュニティの商いに転換することが可能だと思う。というか、持続できそうなかたちを考えて設計したほうがいい。
今の高校の教科書にはZINEづくりについて載っているらしいから、高校生が作ったZINEを店に置くのもいいと思う。あるいは外部講師(といってもZINEづくりできる人は探せば地元にいると思うが)を呼んで制作ワークショップと組み合わせてもいい。大活(大学入試に向けた活動)の一環として探究学習のアウトプットをZINEにしよう、完成したら地元の本屋で販売するよ、といった文脈が作れれば、手間はかかるが客単価も上げられると思う。
教育、子どもの興味、進路に関わることには財布のひもがゆるむのが保護者だからだ。
それと、本屋に自分がつくった本が並ぶのは、純粋に嬉しいものである。とくに初めてのときの感激は自分の体験を振りかえってみても忘れられない。本屋はそういう特別な価値を持っているのだから、お金に換える方法論があると思う。もちろん、かつての自費出版ビジネスのようなあくどいかたちのものはダメだが。
あるいは小中学校では「地元の人に話を聞きに行こう」みたいな授業が社会科などであり、郵便局や商店などに「いつからやっているのか」「どんな工夫をしているのか」とか聞いてまとめているし、職場体験もある。
そういうことがきっかけとも限らないだろうが、子どもはわりと自然体で「地域の人や地域の歴史のことがわかったら楽しい」という感覚があるように見える。
おじいちゃんが書いた個人史(自分史)のように、本人が何も考えずにだらだら書くと「誰が読むねん」というつまらないものになりやすいものでも、子どもを聞き手として呼んできたり、あるいは話を聞く側、編集する側の大人が、ZINEの読者が求めているテーマ、たとえば地域で生きている人たちとの文脈を設定した郷土史や地域の産業史の語りになり、往時の写真が掲載できれば、意味がある資料にもなるし、商品価値のあるものにもなりうる(もちろん、1000部とかは売れないだろうが)。
このあたりは本屋が持っている能力というより編集者やライターのスキルではあるが、客の顔が見えている小売の視点が入ると、より読者に刺さるものにできると思う。
というところで土曜朝の持ち時間が尽きた(子どもと過ごすタイムが来た)のでまた来週。
すでに登録済みの方は こちら