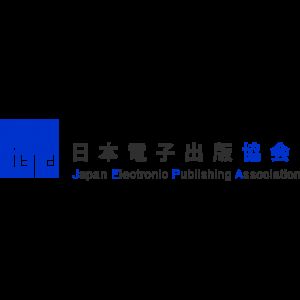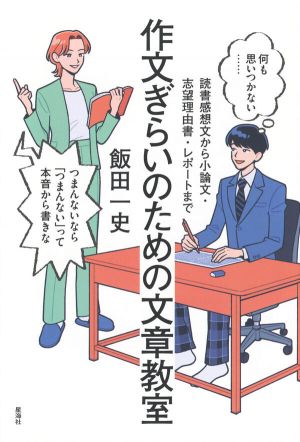2つの電子書籍市場「推計」はどのくらい・なぜ違うのか 出版指標年報と電子書籍ビジネス調査報告書
出版市場について数字をもとに書こうとする多くの人が困惑するのは、電子書籍市場の推計については国内には2つの調査があり、その差があまりにも大きいことだ。今回はその点について少し掘り下げてみたい。
2025年に発売された『出版指標年報』では2024年は5660億円、『電子書籍ビジネス調査報告書』では6703億円。1000億円以上違う。
出版指標年報によれば2024年にはラノベ文庫市場、ラノベ単行本市場いずれも100億円切っており、紙では合わせて200億円もないわけだが、とはいえ「ラノベ5つ分以上違う」と言えば(ラノベの書店での扱いの規模を想像してもらえれば)相当な違いだとわかるだろう。
なお、あらかじめ断っておけば、なぜこんなに違うのかについて私は「答え」を持っているわけではない。両社ともに、推計のロジックは公開していない。私はインプレスの方の国内事業者取材(ヒアリング)には今年から協力しているが、定量データを見たりいじったりできる立場にはない。推測の根拠もないではないが、取材に協力したからこそ「なぜこんなにニュアンスが違うのか?」と疑問に思うところもある。それらをまとめて書いてみたい
1.「年」と「年度」の違い?
2つの調査で明確に異なる点のひとつが出版指標年報のほうは「年」(1月から12月まで)、電子書籍ビジネス調査報告書では「年度」(4月から3月まで)という点だ。とはいえ4か月で1000億円ズレるほど急成長している市場ではない。
インプレスが年度で区切っているのは、年度が切り替わらないと「昨年度の売上はいかがでしたか」とヒアリングしてもあまり情報が出てこないことが理由のひとつである(取材はほぼ4月から5月にかけて行われる)。上場企業であればIRの発表が5月にあることが多く、それらも参照して算出・執筆したものを7月に刊行している。
出版指標年報はそれよりも早く例年5~6月に発売される(今年は6月末刊行)。執筆・編集スケジュールを考えると、2025年発売のものなら「2024年の動向」は、各社の2024年(度)の数値が確定・公表していない段階で書かざるをえない部分が多いと思われる。この点は市場動向の表現のニュアンスに影響があるはずだ。
2.消費税+ポイントで買った分を加味するかどうか
この点がおそらくもっとも大きな違いだと思うし、違いのかなりの割合についてはこれで説明が付くと筆者は考えている。
出版指標年報は「小売り額としての販売金額(読者が支払った金額、税抜き)でカウントしている。一方、インプレスは「日本国内のユーザーにおける購入金額の合計」で算出している。普通に考えるとこれは税込価格である。
つまり、まず消費税10%分が違う。5660億円(税抜)+消費税10%=6226億円。これで差は477億円まで縮まる。
さらに、これは筆者がインプレスの人間から直接聞いた話だが、電子書籍ビジネス調査報告書ではユーザーが各種ポイント(楽天ポイント、dポイント、マンガアプリ内のボーナスコインなど)を使って買った分も「売上」(市場規模)に含んでいる。
なお、公取的な解釈ではポイントサービスは「値引き」である(くわしくは拙著『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』参照)。したがって、もともと大手取次トーハン傘下の出版科学研究所が、商品の額面ではなく「実際にユーザーが支払った金額」でカウントしているのは出版業界的なお作法としては正しい。
とはいえ値引き分のコストを事業者が負担していると解釈して電子書籍全体の「売上」を算出するインプレス式の計算も、理屈としては成立する。
ポイントサービスで何百億円分も違いが出るか?と思うかもしれない。
しかし、国内最大手で合わせて売上2000億円規模のLINEマンガやピッコマは全額還元キャンペーンをしばしばやっている。この期間内に対象作品を買うと、購入金額と同額のボーナスコイン(ただし期間限定)がもらえる、というやつだ。たとえば1万円分買ったら、もう1万円分買える権利がもらえる。1万円で2万円分買える。実質50%引き、言い換えると50%分のポイント還元になる。そしてこれは出版指標年報では1万円、インプレスでは2万円とカウントされる。全然違うのである。LINEマンガとピッコマだけで100億円単位でズレが生じてもおかしくない。
つい先日「市場が伸びて見えるのは、販促費のつぎ込み結果」、つまりポイント還元分を事業者が負担しているだけで市場はもう伸びていないんだ、という意見をパピレスの天谷幹夫氏が書いていたが、これは遠回しなインプレス式の推計方法への批判だと解釈することもできる(ただ、出版科学研究所に対してはこのロジックは成立しないと思う)。
3.それにしても似たようなところにヒアリングしているはずなのにニュアンスがあまりにも違う
筆者が出版指標年報を見ておどろいたのは、電子書籍市場が前年比5.8%増と発表していたことだ。電子書籍ビジネス調査報告書では昨対比3.9%増としている。年と年度の区切りの違いを考えても4%と6%ではだいぶ与える印象が違う(なお、パピレス式の解釈で言えばインプレスの成長率のほうが大きく出ても良さそうなものだが、そうなっていない点に留意されたい。筆者は天谷氏の見解を必ずしも支持していない)。
コミックを除く「文字もの等」(写真集含む)の伸びも出版科学研究所のほうは2.7%増、インプレスの方は2%増と全体に出版科学研究所のほうが強気である。
『出版指標年報』2025年版には「ライトノベルは電子書籍では売れ行きを伸ばしている。シリーズものが多く、割引などの施策も効果的で、電子との親和性は高い。デジタルシフトが進行していると思われる」とあるが、筆者が今年の春に国内電子書店事業者や電子取次にヒアリングした際に「ラノベが好調。伸びている」などと語った会社は一社もなかったので、ここを読んだときには「え?」と思ってしまった。
しかもよくよく出版指標年報の記述を元に計算してみると、出版科学研究所は自ら発表している数字とその評価が乖離していることがわかる。ラノベ文庫本の推定販売金額は前年比18.2%減の81億円、単行本ラノベは15.7%減の86億円で前年比34億円も減っている。一方、電子書籍の文字もの等は452億円で前年比2.7%増、つまり約12億円しか増えていない(実際には増加分は写真集の伸びが大きいだろう。この点については国内電子書店の多くから聞こえてきた)。仮に伸びた分すべてがラノベだったとしても、紙で34億円減り、電子で12億増えただけなら差し引きは大幅にマイナスだ。これをもって「デジタルシフトが進行している」などと言うのはおかしい。もしやKADOKAWAの担当者が盛った話を鵜呑みにしただけなんじゃないかと邪推したくなるレベルである。
なぜここまで違うのかについて筆者は答えや推論の根拠を持っていないが、算出ロジックの違いだけでなく、各事業者からのヒアリングの解釈も相当に異なるであろうことは注意喚起をしておきたい。
簡単に言えば、
・出版科学研究所は、売上のカウントの仕方は保守的だが、市場の見方は楽観的
・電子書籍ビジネス調査報告書は、売上のカウントはアグレッシブだが、市場の見方は保守的
である(少なくとも2025年においては)。
■告知
本の定価販売がないオーストラリアでも「本の値上げがむずかしい」と中小版元が言っているという話を書きました。
「道徳と特別活動」2025年8月号のリレー連載企画「今、君たちに伝えたいこと」に「あたりまえのようでいて、変わっていく景色を残す」と題したエッセイを書きました(小学生向け)。
「東京人」2025年9月号に「生活の書店体験。」というエッセイを書きました。
8月26日(火)横浜ネイキッドロフトで横浜の本屋の歴史と現在について中岡祐介さんと語ります。年表も作っているのでpdfで配布します
8月18日に鳥取県図書館大会で若者の読書について講演します。
8月29日(金)から双子のライオン堂&オンラインで『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』解説講座をやります。隔週全3回。書店員・司書・学生割引あります。ぜひ。
新刊出ました。作文や小論文の個別の書き方のパターンを教えるのではなくて、もっと汎用的に、その前に考えるべき点を整理しているのが特徴です(十代向けに、文章執筆でも日常生活のコミュニケーションでも使える、クリティカルシンキングやマーケティングの考え方の基礎の基礎を解説している本でもあります)。
また、書くのに詰まってしまったり、だめだめな文章になってしまったりするのは実はメンタルの問題が大きいので、そこをほぐすことにも力を割いて書いています。
すでに登録済みの方は こちら