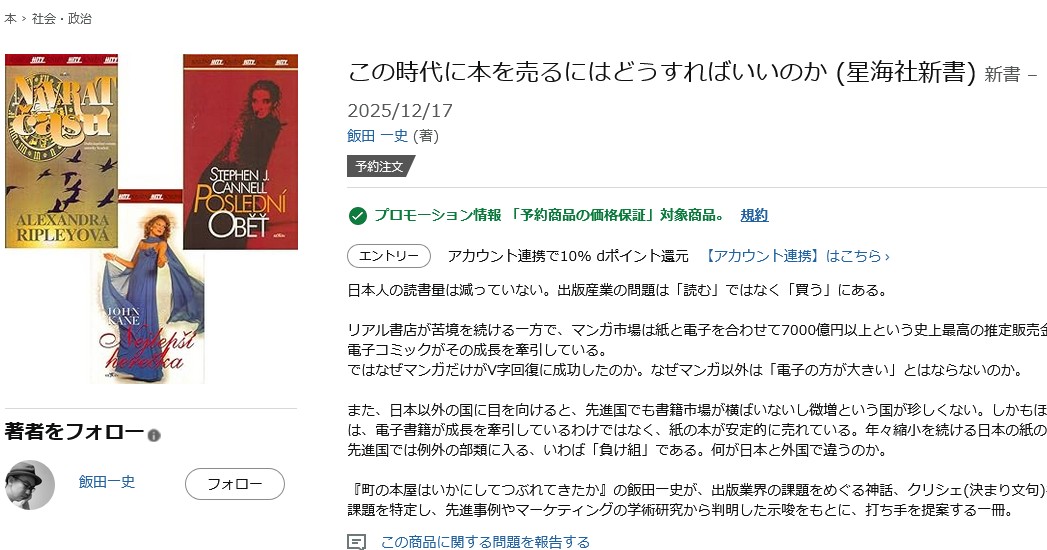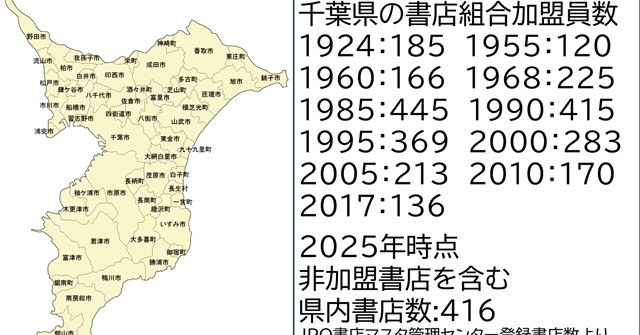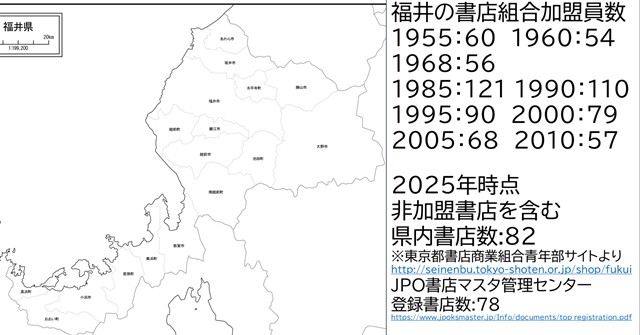子ども向けの本の実用性(勉強、しつけ)重視化?
勉強になる子ども向けの本といえば、学習マンガは60年代からあると言われています。市場が巨大になったのは80年代以降であり、2000年代以降は「サバイバル」の影響でストーリー性やキャラクター性重視のSTEM系ものが増えました。
キャリア教育要素もありますね。
まあ個人的には読書推進政策の後押しを受けて「児童書」である「学習マンガ」は売れ、その恩恵を被ることができない「児童マンガ」が売れなくなっているという市場のゆがみはどうかと思っているのですが……。
小学生向けの小説でも科学もので人気の作品があります。まあいかにもお勉強っぽい話でなくても、英米のYAでは反差別とか多様性重視とか気候変動問題とかが自然と入っていて、それが一部では「説教くさい」とも言われるわけですけれども。
子ども向け実用・自己啓ジャンルの確立は2010年代以降ですね。
旺文社はもともと大人向け自己啓を分析して、その分類を子ども向けに応用して作っています。
で、懐事情(可処分所得減、書籍代減)から「親子で読めるもの」需要の高まりもこういう本の売れ行きを後押ししている。
子ども向け実用の効用として、発達障害の子どもが親から何回も口で言われても理解できなかったことが文字と絵でまとめて書かれたことでやっとわかった、という話もあります。
ここで西東社の人が言っているのですが、実用・自己啓だけでなく、歴史学習本に関しても「下に広げる」つまり低年齢向けに展開していく傾向があります。小学校では中学年から社会科が始まりますが、保護者のニーズとしてはもっと早くから(人によっては未就学児から)触れさせたいというものがある、と。
歴史だけでなく地理もそうですね。『にゃんこ大戦争』の地理学習本は実際見ると低中学年向けです。うちの小1の息子もにゃんこ好きなのでちょっと読んでました。
学習参考書もライト化が進んでいて、キャラものの「ライト学参」が『カゲロウデイズで学ぶ』『ボカロで覚える』あたりから一般化しました。見やすく、親しみやすくと。あと学参ってもともとは家でひとりで勉強できる人向けだったのを、学研がパイオニアになって低~中偏差値層に広げたんですよね。実用性や勉強要素のある児童書もそういう流れにあると言えるかもしれません。ほっといても骨のある文字ものの本を読む層向けにかつては子ども向けのポピュラーサイエンス本とかがあったのが、今は裾野を広くして偏差値的にボリュームゾーンにいる層向けを狙うようになった、と。
加えて、学習や実用性に関してエビデンス重視になったのは睡眠の専門家が監修して「効果が実証済み」と謳われた『おやすみ、ロジャー』の翻訳(2011年)がヒットして以降じゃないかなと思います。だからこの10年くらいでしょうね。
ところがそうやってあれこれ詰め込まれて育っても中高生になって自分で本を選ぶようになると、明らかに自己啓的な「目標を立ててがんばろう」的なものと逆の「そのままでいい」的な自己慰撫的な本を選ぶようになるのが皮肉です。
すでに登録済みの方は こちら