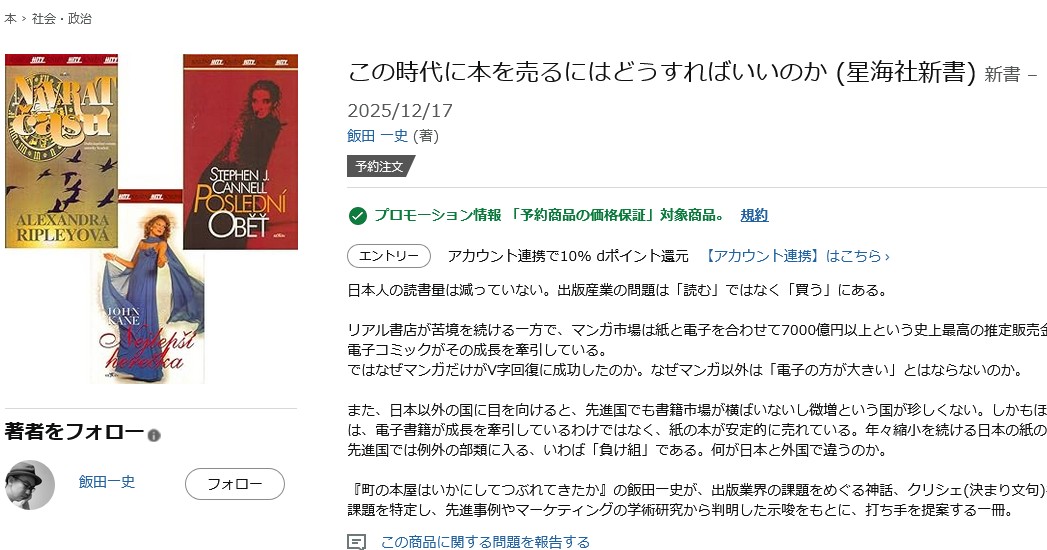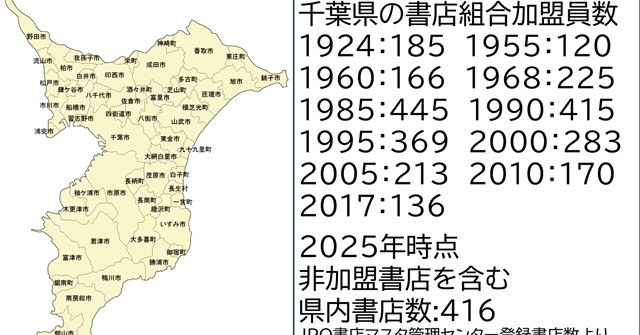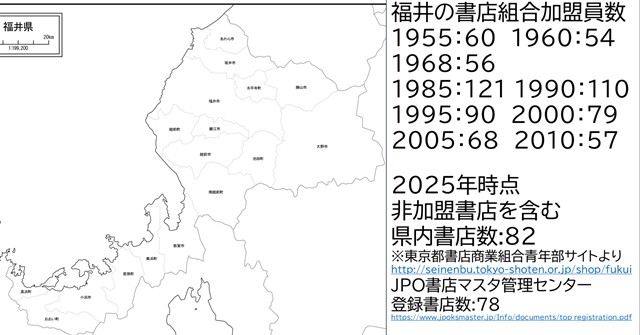日本のウェブトゥーン産業の課題
3月のレッドセブン(レッドアイス日本法人)イ・ヒョンソクさんの記事
に引き続き、ウェブトゥーンの歴史についてインタビューしました。
Plott×ソラジマ対談
でも言っていますが、僕が日本のウェブトゥーン産業の課題だと思っていることをまとめると
1.白黒マンガよりスタジオシステムで制作するとコストが3倍かかるのに、市場規模は白黒マンガの3倍ない(日本においてはもちろん、全世界合わせても3倍はない)のに、リスクヘッジの手段が白黒マンガより少ない
読み切り→集中連載→連載といった読者の反応を確認しながらステップアップしていくしくみがない。いきなり連載し、かつ、最初に一気に数話とか20話納品しないといけない。
韓国であるような、自由投稿プラットフォームで人気になった作品・作家をフックアップするしくみが日本ではcomicoくらいでしか機能していない(comicoも十分とは言えない)。
同様に、自由投稿プラットフォーム発のウェブ小説で人気になった作品をウェブトゥーンにするしくみも不十分。
結果、当たる見込みが低い(よく言えば「未知数」な)企画に高いコストをかけて制作してしまっている。
2.有効性が確立されたプロモーションツールが、プラットフォーム(ストア)側が出す広告くらいしかない
白黒マンガの場合、販売に影響力のあるアワードがいくつかあり、専門ニュースサイトがあり、本紹介サイト等でレビューが無数に書かれ、SNSでバズが起こり、出版社の書店店頭や電車その他でのプロモーション方法が確立されている。また、アニメ化、実写化、各種商品展開のセオリーができており、それらがアップセルだけでなくさらなる認知拡大につながる。
一方、日本のウェブトゥーンではピッコマやLINEマンガが展開するサービス内外の広告に取り上げられるかどうかによってランキングに入るかどうかが大きく左右され、ランキングに入るかどうかが長く売れるかどうかに関わってくる。だけ、である。現状、有効な売り方が非常に限定的な状況にある。
……ということを前提に、日本以外の国では「ウェブトゥーンの販売」をどうやっているのかについて10月21日~23日に開催されるIMART2022に登壇してトークします(僕は司会)。
エージェントとして韓国ウェブトゥーンを各国の事業者とつないでいる宣政佑(ソン・ジョンウ)氏に出ていただきます。ほかに中国や東南アジアの動向を語れる方々と調整中です。宣さんが韓国なのでこのパネルはリモートによる事前収録になると思いますが、ご興味ある方はぜひご参加ください。
すでに登録済みの方は こちら