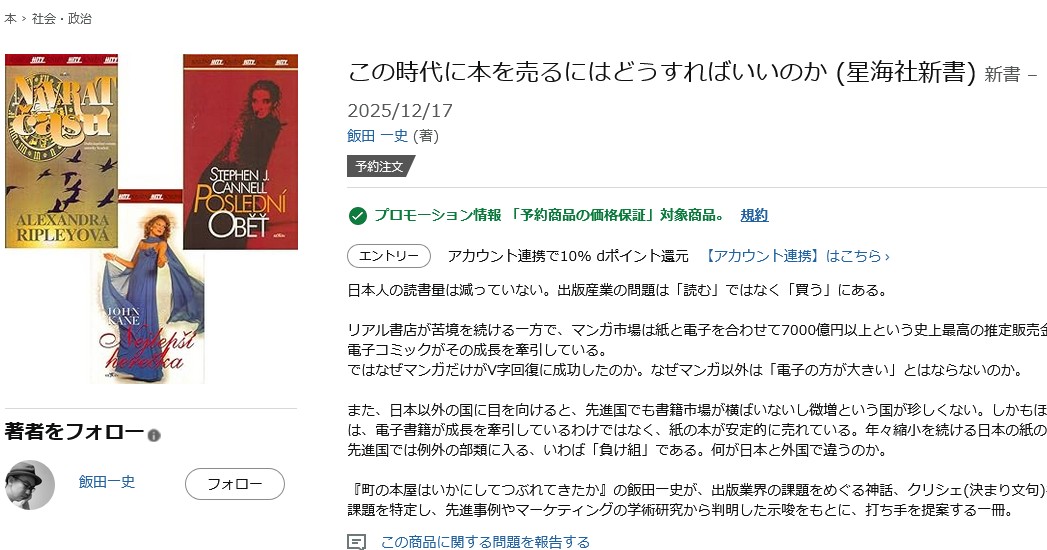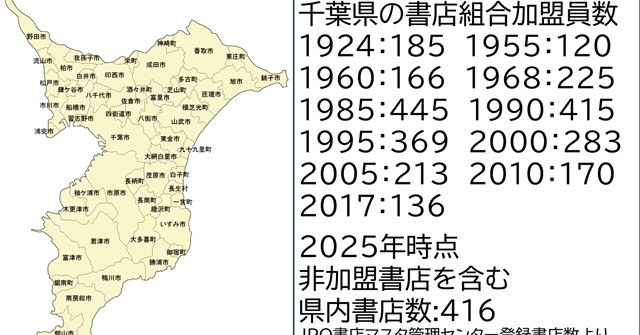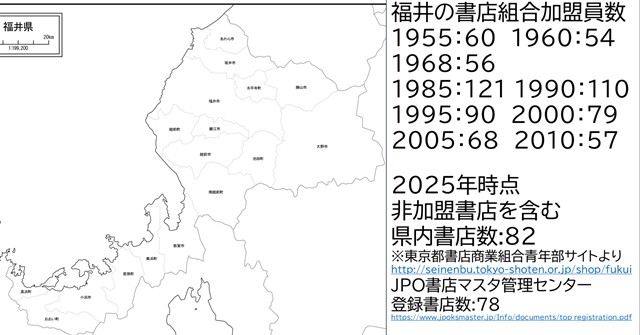『ブック・ウォーズ』に学ぶアメリカの出版産業&なぜ出版ではサブスク型読み放題が限定的なのか
本Newsletter購読者の方にはぜひ手元に置いておいていただきたい一冊である。しかし700ページ以上、約6000円することもあるので、どういうところがおもしろいのか少し紹介した上で、筆者なりに日本への示唆を考察してみたい。
■ブック・ウォーズの読みどころ①アメリカの出版作業の基礎知識が手に入る
『ブック・ウォーズ』はアメリカの出版産業におけるデジタル革命以前と以後の変貌をまとめた大著だが、変化を記述するために「その前はどうだったのか」を丁寧に書いてくれている。これはアメリカにいない人間にとってもありがたい。出版社や書店にどんなプレイヤーがおり、どういう商慣習やプロモーションが行われてきたのか、宣伝予算の相場はいくらなのかといったことがわかる。北米進出を考えている/既にしている事業者にはもちろん必読だし、日本の出版産業でも参考になる。
たとえば従来は、大型書店やウォルマートなどを中心に小売店の販促費用の一部を負担することで店頭スペースや陳列台での露出を確保する「共同広告」(co-op)と呼ばれるプロモーションが重視されてきた(今もされている)。
筆者の知る限り、日本の書店業界では一般的な取り組みではないと思うが(ただ音楽業界、CDショップでは平積みさせるためにレコード会社が小売店のスペースを買って販促することは普通に行われてきた)、シェア型書店は棚主がお金を出して書店のスペースを買っているので、ビジネスモデルとしては似ている。
アメリカの出版社は新刊本のマーケティング予算を、通常、予想される収益の一定割合(たとえば6.5パーセント)で設定する。もちろん本の種類や予想される売上によって予算は大きく異なり、5000ドル~50万ドル程度まで幅があるという。マーケティング担当者は、この予算内で効果的な宣伝方法を模索する。
日本では書籍に関して予想収益の5%~6%もプロモーション予算は割かれていないだろう。書籍は出たとこ勝負が大半であり、書店に撒いてみて売れたものに予算を付けてさらに売り伸ばす方が長年主流だった(もちろん前パブに力を入れている出版社も今では少なくないが、伝統的には)。
アメリカでは雑誌と書籍は販売店自体が異なり、日本のように雑誌のついで買いで書籍を売るモデルは成り立たないため、書籍単体で採算が取れるよう売るために宣伝予算を付け、事前予約期間を長く取ってきた。日本も雑誌が凋落したのだから書籍の売り方や価格設定、予算取りは欧米式に近づけていく必要がある。
このように彼我の違いがわかるし、参考にできそうな点も見つかる。
■ブック・ウォーズの読みどころ②出版産業でなぜ定額型読み放題サービスは限定的なのか
(ここでは2点にまとめたが、読みどころや情報量があまりに多い本なので、ほかにも記事を書いている。そちらもよければ読んでいただきたい)
日本でもよく(とくにマンガ業界では)「なぜ出版では音楽や映像のように定額で読み放題のサブスクリプション型モデルが広がらないのか」と語られてきた。
その点に関して『ブック・ウォーズ』は北米の事例から論点や各プレイヤーの思惑を見事に整理している。
1.主要なサブスク型サービスと棲み分け
まったくないわけではなく、日本でも著名なAmazonのKindle Unlimitedと、SlideShareで知られるScribdの同名サービスの二系統がある。前者はKDPで配信されているセルフ・パブリッシングのタイトルが圧倒的なシェアを占める一方、ビッグファイブと呼ばれる超大手総合出版社のタイトルはほとんど提供されていない。Scribdは逆にビッグファイブのうちのいくつかと提携しているが、KDPでもっとも強いジャンルであるロマンスなどは配信していない。
なぜこうなっているのか。
2.ビジネスモデルの違い
Kindle Unlimitedはサブスクリプション収入の一定割合が著者への支払いプールとして確保される(ロイヤリティ・プール・モデル)。各著者への支払いは、全体の読書量に対する当該著者の作品の読書量の割合に基づいて計算される。
つまり何ページ読まれたかによって著者の印税が自動的に決まるわけではない。この点がビッグファイブの出版契約書ではネックになる。普通は電子書籍については「出版社から小売店への卸値は○ドル。1部売れるごとに売上の何%支払う」というような契約になっているからだ。電子書籍が売れた場合と比べて大幅にそれを下回る支払いしか発生しない(ことが多い)点をよく思わない著者もいる。