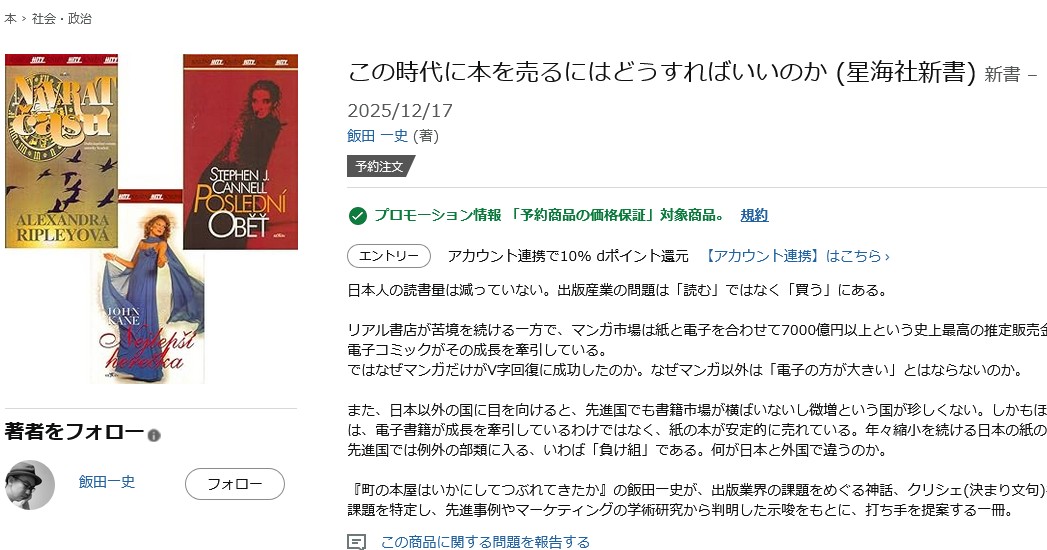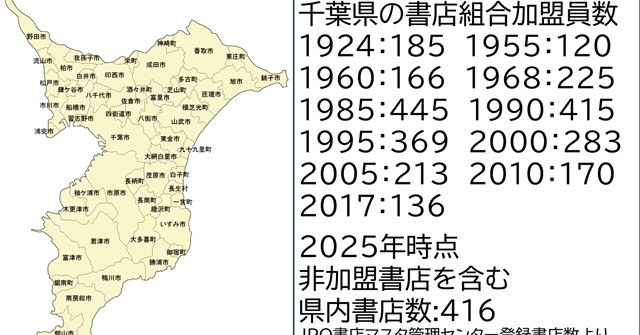インドのコミック産業
Netflixはインドがアニメコンテンツ視聴者数で世界第4位にランクインし、3,000万人以上のアニメ視聴者がいると報告した。
また、Crunchyrollはインドのアニメファンが1日平均60分以上アニメを視聴していると言っている(https://www.thecurrent.com/anime-india-streaming-gaming)。
この記事では「インドは中国に次ぐ世界で2番目に大きなアニメ市場で、推定1億8000万人のアニメファンがおり、彼らは世界のアニメ成長の60%に貢献すると予想されている」とまで言っている。
2023年12月にはエイベックス・ピクチャーズや集英社など13社が出資する合弁会社が、Amazon Prime Videoでインドの「Anime Times」チャンネルへの配信を開始した。
このようにアニメでは非常に注目されているが、ではマンガの参入余地はあるのだろうか。インドのコミック産業はどうなっているのか。
■インドのコミック産業の歴史
フラフィックノベル作家でリサーチャーのキリティ・ランバトラによれば(https://www.linkedin.com/pulse/indian-comics-billion-dollar-industry-reeling-under-sector-rambhatla)、インドのコミック市場を1億ドル~1億5000万ドル(米ドル)と推定する向きが多いが、流通システムが断片化され、インドの書籍市場は90%が組織化されていないため、やはりわからない(測定されてもいない)という。駅や食料品店、路上でも本が売っている。
※そもそも教科書を除く書籍市場が150億円と推定されているのに、コミック市場だけでほぼ同規模の1億ドルもあるわけがないと思う。
インドのコミック産業の定量的な実態はよくわからないが、歴史についての論文はいくつも書かれている。少し紹介してみよう。
1947年以来、子ども向けのイラスト付き月刊誌「チャンダママ (Chandamama)」があったが、そこでは西洋のキャラクターだらけだった。
1960年代初頭の新聞漫画家において、外国のコミックストリップの独占を打ち破り、インドに最初のコミックキャラクターであるティーンエイジャーのダブ (Dabu) と彼のメンターであるアディカリ教授 (Professor Adhikari) が誕生する。ヒンディー語のユーモア雑誌「ロトポット (Lotpot)」のために作成された「チャチャ・チョードリー (Chacha Chaudhury)」は10の言語で何百もの漫画本が出版され、1000万部以上を売り上げ、インドでもっとも知られるキャラクターのひとつになる。この漫画はのちに「ダイヤモンド・コミックス (Diamond Comics)」でも出版された。
チャチャは実写とアニメの両方のテレビシリーズで21世紀に入っても人気を保っている。
1964年に初のコミックブック・レーベル「インドラジャル」から『ファントムのベルト』(ヒンディー語でヴェタル・キ・メクラ)が発売される。同作は大流行し、1970年代にデリーで書店を経営していたダイヤモンドコミックスのグルシャン・ライは「人々はインドラジャルの新しい号のために店の前に列を作っていた」と回想する。
1970年代、インドのマンガは一般的に1コマまたは1~2ページしかなかった。ムトゥコミックスがUKで人気を博した「ザ・スティール・クロウ」をタミル語に翻訳・出版し、書籍としてコミックブックを出版したインド初の出版社となる。
インドのコミックの黄金期は1980年代後半から1990年代前半だとされる。
この時期にRaj Comicsなどの出版社を通じて「スーパーヒーロー」というジャンルがインドのコミック界に登場し、ヒンディー語圏で大きな支持を得た。インドのコミック文化がほとんど消滅していた時期に参入したラジ・コミックスは、キャプテン・ドルーヴァ、ナグラージ、ドーガのようなキャラクターを生み出し、子どもやティーンエイジャーの間で非常に人気になった。ラジ・コミックスは35,000冊近くのコミック、5,000タイトル、20キャラクターを出版する。
1992年に発売されたナグラジ・エア・ブガクというタイトルのラジ・コミックスの作品は、発売3か月で60万部以上を売り上げ、インドでもっとも売れた漫画になりました。
また、インドを代表する漫画出版社のひとつマノジ・コミックスも、90年代には1年以内に365以上の漫画を出版していた。
1994年にはインディーズ漫画クリエイターのオリジット・センが、多くの人が「インド初のグラフィックノベル」と呼ぶ『リバー・オブ・ストーリーズ』を出版。政治的に激しいナルマダ川流域プロジェクトに基づき、子ども向けの皮をかぶって深い物語を展開した。
実際に「売れた」部数以上に、1980年代から90年代にかけてインドの子どもたちは地元書店から1日1ルピーか2ルピーで大量のコミックを「借りて」読んだ。
しかし、1991年にインド市場が開放され、衛星テレビ市場に大きな変化が起こると、インドのコミック読者はそちらに移る。このとき『ドラえもん』など日本のアニメもテレビ放映された。
1997年には米国の会社ゴッサム・コミックスがインドで設立され、コミック雑誌と児童書の市場でリーダーとなる。